旧民法から現在までの法定相続人の変遷
公開日:2025-09-29 00:00
目次
相続のルールは時代とともに変化してきました。
そのため、何代も前の相続がそのままになっていると、今のルールとは違う扱いになっていることもあります。
たとえば、かつての「家督相続」が関わるケースでは、相続人の範囲が今よりずっと狭くなることもあります。
こうした法定相続の変化は、配偶者の立場や個人の権利が徐々に認められてきた歴史のあらわれです。
単なる法律の決まりごとではなく、社会の変化を反映して今に至っていると知ることで、相続の見方も少し変わってくるかもしれません。
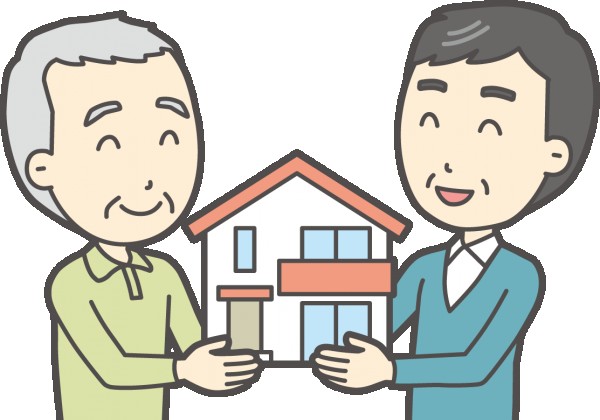
■ 相続登記義務化「後」の今
まず、相続登記が義務化について触れたいと思います。
相続登記は、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、
相続登記がなされていないものは、義務化の対象となります。
(但し、3年の猶予期間があります)
この義務化ですが、正当な理由がないのに、
相続登記の申請をしないと10万円以下の科料が科される可能性があるとのことで、
このままにしておくといけないと思った方々が、相続の相談と同時に相談されることも増えました。
そうなると、相続人の特定も大変になりますし、話がまとまるまで非常に時間もかかります。
話がまとまらないときはもっと大変です。
はたまた、建物の登記がなされていない場合も、いまだによくあるケースです。
ただ、登記を行う前提段階でまず相続人の特定が必要となります。
実は、法定相続人は、時代と共に民法の規定で変化しています。
よって、相続が発生した当時の民法で法定相続人を考える必要があります。
ここから旧民法から現在までの法定相続人の変遷をお伝えします。
■ 法定相続人の移り変わり
【相続開始が明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで】
明治31年7月16日施行の旧民法が適用されます。
最大の特徴は、家制度を基盤とする「家督相続」と「遺産相続」の2種類の存在です。
◉「家督相続」は、
・戸主の死亡、戸主の隠居、戸主の日本国籍喪失などが開始原因となり、戸主家督相続人は1人に限定(単独相続の原則)、戸主の地位だけでなく財産債務、祭祀についてその家に関するすべての権利義務も承継する。
・「家督相続」は、基本的に戸籍に記載されているので、新しい戸主がすべての財産を承継していると考えられる。
では、
◉ 旧民法の「遺産相続」とはどのようなものでしょうか。
・ 遺産相続の開始原因は戸主以外の家族が死亡した場合。
・ 配偶者は直系卑属がいない場合にのみ相続人になる。
・ 兄弟姉妹は相続人にならない。
・ 一番注意したいのが、隠居した旧戸主が死亡した場合も遺産相続に該当するということです。つまり、不動産の登記をみて、所有権をいつ取得したかによって、家督相続なのか遺産相続かが変わってきます。
【遺産相続の法定相続分】
|
第1位 |
直系卑属 親等の近いものが優先 胎児はすでに生まれてものとみなす |
同順位の相続人が複数ある場合、共有となる 非嫡出子は嫡出子の2分の1 |
|
第2位 |
配偶者 |
|
|
第3位 |
直系尊属 |
|
|
第4位 |
戸主 |
|
【相続開始が昭和22年5月3日から昭和22年12月31日まで】
日本敗戦後、日本憲法が施行されました。
憲法24条において、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めたことから、旧民法との矛盾が生じました。
そのため、応急措置法を適用することになります。
その特徴は、下記のとおりです。
・配偶者が常に相続人となる。
・兄弟姉妹の相続が第3順位の相続人となる。
・非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1。
・兄弟姉妹の相続は全血及び半血の差異はない。代襲相続もない。
【遺産相続の法定相続分】昭和22年5月3日~昭和22年12月31日
配偶者と直系卑属 | 配偶者 3分の1 | |
第2位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者 2分の2 |
第3位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3分の2 |
【相続開始が昭和23年1月1日から昭和55年12月31日まで】
日本国憲法施行後、昭和23年1月1日から施行された民法の親族相続編が適用となります。
大きな特徴は、
・半血の兄弟姉妹の相続分が、全血の兄弟姉妹の2分の1とされたこと。
・兄弟姉妹にも代襲相続制度が認められたことです。
法定相続分については、上記応急措置法の表と同じです。
【相続開始が昭和56年1月1日から平成25年9月4日まで】
昭和23年に施行された民法は、社会や家族の在り方の変化に伴い、改正されていきます。
昭和37年には、法定相続分に変わりはありませんが、同時死亡の推定規定、相続放棄者は初めから相続人でないとされることなど、重要な改正もありました。
その後、昭和55年においても、民法は大きく改正され、法定相続分においても下記の通り改正されました。
【遺産相続の法定相続分】昭和56年1月1日から平成25年9月4日
|
配偶者と直系卑属 |
配偶者 2分の1 |
|
|
第2位 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者 3分の2 |
|
第3位 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 4分の3 |
・非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1
・半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1
【!要注意!平成13年7月1日以降に開始した相続について】
平成25年9月4日、最高裁判所は、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1とする規定につて、憲法14条1項(法の下の平等)に違反しているとの決定をしました。そして、嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とする取扱いとなったのです。
注意したいのは、最高裁判所は、平成13年7月において非嫡出子と嫡出子の相続分規定は違憲であったと判断しています。
この違憲判決により、平成13年7月以降の相続において、遡及的に嫡出子と非嫡出子の相続分は同等と扱うことになります。
ただ、すでに、遺産分割協議や裁判等が終了しているものについては、その効力に影響はありません。
(平成25年9月4日最高裁判例:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520)
【相続開始が平成25年9月5日以降】
平成25年12月11日に非嫡出子の法定相続分違憲判決を受けた改正民法が施行されました。
【遺産相続の法定相続分】平成25年9月5日以降
|
第1位 |
配偶者と直系卑属 |
配偶者 2分の1 |
|
第2位 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者 3分の2 |
|
第3位 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 4分の3 |
・非嫡出子と嫡出子の相続分は同等。
・半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1
■ 相続人を正しく確定することの大切さ
今回のコラムは、法定相続分にフォーカスして民法改正を追ってきました。
昭和23年以前の相続のご相談を受けることも珍しくないため、「正しい法定相続分を知り、相続人を確定する」ことは、相談の最初の一歩であると考えています。
さて、民法改正は法定相続分だけでなく、私たちの様々な大きな生活の変化を反映してきました。
是非ほかの改正についても、見ていただけると興味深い変化を発見できると思います。
今、日本は急速に超高齢化少子化社会に進んでいます。
現在の民法では立ち行かない場面も出てくるかもしれません。
次に民法が改正されるとき、私たちの家族や婚姻や相続はどのように変化しているのでしょうか。
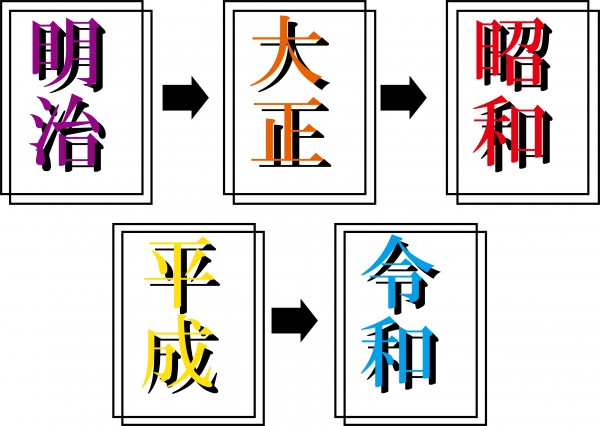
蓮見 倫代(はすみ みちよ)
行政書士(東京都行政書士会所属)
わらし行政書士事務所 代表
成年後見サポートセンターコスモス埼玉所属

「自分らしく生きる」「物も想いも、まるごと次の世代へつなぐ」――
そんな相続や終活のあり方を、一人ひとりに寄り添いながらサポートしています。
20年近く法律事務所に勤務した経験を活かし、相続発生後の銀行手続きや名義変更などの相続手続きを中心に、遺言書作成やエンディングノート活用、家族信託など幅広いご相談をお受けし、相続や終活に不安を感じている方が、「笑顔」で次のステージに進めるよう、心を込めてお手伝いします。
【保有資格】
行政書士
相続診断士®
笑顔相続道正会員
縁ディングノートプランナー®
【筆者へのお問い合わせ】
わらし行政書士事務所
E-mail: m-hasumi@wrashigyo.com
HP: https://warashigyo.com/
所在地: 東京都新宿区新宿1-6-5 シガラキビル5階


