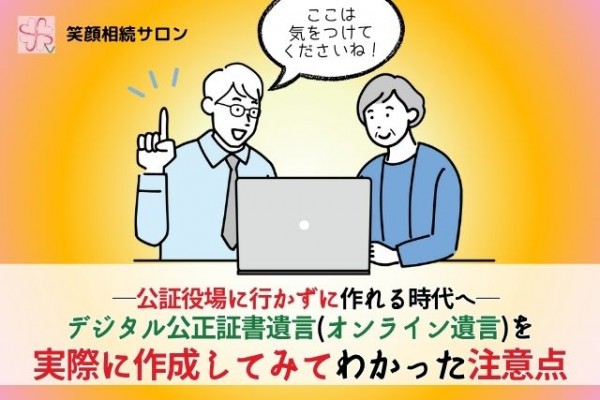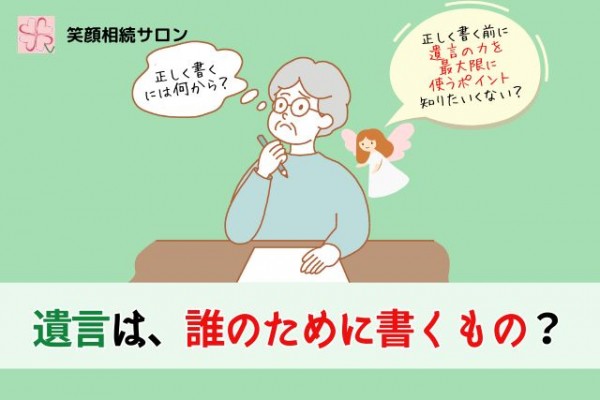家庭裁判所が使う“遺産分割の6ステップ”で相続が見える化する! 〜調停モデルは思考整理と遺言作成にも使えるフレームだった〜
公開日:2025-08-18 00:00
目次
■ 相続は「揉める前提」で考える時代に
今や「相続トラブル」は、ごく普通の家庭でも深刻な対立が起きる時代です。
むしろ、財産の額が中途半端だからこそ揉めやすいという現実もあります。
家庭裁判所での遺産分割調停の件数は堅調に推移しており、「話し合いで終わらない相続」は、もはや特別な話ではありません。

■ なぜ、相続で揉めるのか。
その背景には、以下のような事情があります。
・親族関係の希薄化:親族間の付き合いが減り、相手の事情や価値観が見えない
・財産の複雑化・不動産偏重:分けづらい不動産が中心となることで対立が深まりやすい
・高齢化・長寿化に伴う“介護の不公平感”:「自分だけが介護を担った」という不満が表出
・遺言書の不備や曖昧な表現:結果として「解釈の争い」に発展
さらに、「うちの家族は仲がいいから大丈夫」という言葉ほど、危うい前提はありません。
生前は良好だった関係も、相続という“利害の交錯点”を迎えた途端に緊張が走ります。
こうした現実を踏まえると、「争いを避けるための対策を、前もって講じておくこと」こそが、重要な相続準備といえます。
そして、そのためには、単に遺言書を書く、信託契約を結ぶという表面的な手続きだけでなく、相続全体の構造や流れを、相談者さん自身も理解し、思考を整理することが欠かせません。
今回の記事では、家庭裁判所が用いている「段階的進行モデル」が、一般のかたにとっても“相続を整理するための優れた地図”になることをご紹介します。
■ 家庭裁判所の“段階的進行モデル”とは何か?
相続トラブルが家庭裁判所に持ち込まれると、「遺産分割調停」という手続きが開始されます。
この調停は、ただ感情的な言い分をぶつけ合う場ではありません。
実は、裁判所はある一定の「順序」に従って、論点を段階的に整理していく進行モデルを用いています。
■ 裁判所で使われる6つの進行ステップ
この進行モデルは、以下の6つのステップに分かれています。
- 相続人の範囲の確定
まずは「誰が相続人か」を明確にします。戸籍をたどり、隠れた相続人がいないかを確認する段階です。
養子縁組、認知、相続人の廃除といった課題を確認する段階です。 - 遺言の有無・遺産分割協議の有無の確認
次に、遺言書があるかどうか、過去に有効な遺産分割協議が済んでいないかを確認します。 - 遺産の範囲の確定
相続の対象となる財産を「何が」「いくら分」存在するかを明らかにします。
預貯金・不動産・有価証券など、あらゆる財産の存在の有無を確認します。 - 遺産の評価の確定
財産の種類によっては、相続時点での評価額に争いが生じることがあります。
特に不動産や非上場の株式などは、鑑定や専門的評価が必要になるケースもあります。 - 特別受益・寄与分の主張と整理
生前贈与や介護の貢献などがあれば、それを法定相続分に加算する必要が生じるときもあります。 - 具体的な分割方法の決定
ここまでの論点が整理されたうえで、ようやく「誰が何を取るのか」の話し合いが始まります。
不動産を誰が取得するか、預金はどう分けるか、代償金をどう支払うかといった調整が行われます。
裁判所は、この順序に沿って議論を進めることを原則としています。
この進行モデルは、感情が先行しやすい相続問題において、論点を冷静に分解し、段階的に整理するための非常に合理的なアプローチです。
言い換えれば、家庭裁判所が長年の経験から作り上げた「相続問題の解き方の手順書」と言ってもいいでしょう。
そしてこのモデルこそ、相続人自身が相続を見通すうえで、また遺言や信託を事前に設計するうえで、非常に有用なフレームワークになるのです。
1. このモデルは、相続人が自分で整理するのにも使える
家庭裁判所の遺産分割調停で使われている、この六つのステップは、何も裁判所だけの特別な手続きではありません。
むしろこの「段階的進行モデル」は、相続対策を冷静に考えるための思考整理のフレームとして、そのまま活用できると考えています。
例えば、以下のような場面でも力を発揮します。
・感情的な主張を抑え、論点の順序をそろえる
・話し合いの「土台」を可視化して、建設的な議論に変える
・「今どのステップの話をしているか」がわかることで、無駄な混乱やすれ違いを回避
②
相続財産の棚卸しや、専門家に相談する前の準備として
・預金通帳、不動産登記簿などをステップ3にまとめて整理
・「専門家に何を相談すべきか」が明確になり、相談の精度が格段に上がる
事前にこのステップに沿って情報を整理しておくことで、いざ相続が発生した際の家族間のコミュニケーションが円滑になり、専門家への相談も的確になります。
2. 遺言書を作成する前にこのモデルで準備すると安心
「とりあえず遺言書を書いておけば安心」——
そのように考えてご相談にいらっしゃる方は少なくありません。
しかし現実には、「せっかく遺言を残したのに、かえってトラブルの火種になってしまった」というケースも数多く存在します。
その原因はひとえに、遺言の中身が薄い/不十分/想定が甘いことにあります。
遺言書は、単に「長男に土地、次男に預金を」と書けば済むものではありません。
誰に何を、なぜそう分けるのか、その背景事情まで含めて整理された遺言でなければ、相続人にとって納得感のある「遺産分割の地図」にはなりません。
このモデルを使って、遺言者本人が自らの相続を六つの視点から俯瞰することで、「抜け」や「矛盾」のない遺言の設計が可能になります。
3. 遺言作成における6ステップの活用例
1) 相続人の範囲を明確にする
認知した子どもがいるか、過去に離婚歴があるか。—法定相続人を曖昧にしないことが大前提です。2) 過去の約束・口約束を洗い出す
「長男に家を継がせると昔から話していた」「次女には学費を多く出した」など、感覚で伝えてきたことも一度棚卸しをしてみましょう。
3) 遺産の全体像を把握する
不動産、預貯金、有価証券、負債まで含めた一覧を作成。これが「遺産目録」のたたき台となります。4) それぞれの資産の評価を確認する
不動産の固定資産税評価額や、銀行残高、有価証券の現在価値を把握。遺留分侵害額請求など、後のトラブル防止につながります。5) 特別受益や寄与分を考慮する
生前に援助した子がいるか?介護を担ってきた家族がいるか?といった観点や、遺留分への影響もここでシミュレーションしましょう。6) 分割のシナリオを複数検討する
例えば「不動産を長男に」と書いた結果、ほかの相続人に不公平感が生まれないか?代償分割・換価分割も含めた選択肢を検討することとなります。
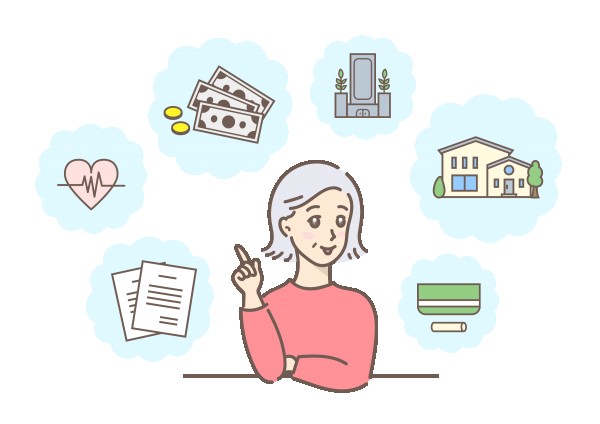
このように、家庭裁判所モデルの順番に沿って自分の財産と相続関係を一度整理してみることで、遺言者自身が、自分の相続のリスクを事前に“見える化”できるのです。
実際、筆者が遺言書の作成支援を行う際も、この六つの項目をヒアリングの骨格とし、丁寧に情報を掘り起こしていきます。
「争わない相続」は、偶然には生まれません。
理詰めで構造を捉えたうえで、“家族への想い”を言語化する作業こそが、安心の遺言書作成の本質です。
■ まとめと提言
相続は、「起きてから考える」では手遅れになることが少なくありません。
特に、遺産の額や家族構成にかかわらず、どんな家庭にもトラブルの火種が潜んでいるのが、現代の相続のリアルです。
今回ご紹介した、家庭裁判所の「段階的進行モデル」は、もともとは調停を円滑に進めるために設計されたものです。
しかしその本質は、相続という複雑な問題を、感情ではなく論理と順序で整理していく“思考の地図”にあります。
つまり、これは、専門家だけが使う手法ではなく、一般のかたにこそ使っていただきたい「争族回避の実践ツール」なのです。
それは、家族の絆をどうつなぎ、次世代に何を託すかを考える行為でもあります。
法的手続きや形式にとらわれる前に、まずは今回ご紹介した六つの視点から、ご自身の家族・財産・想いを見つめ直してみてください。
私たち、終活・相続の専門家は、“納得の相続”を一緒にデザインするパートナーでありたいと願っています。
【筆者プロフィール】
大石 誠(おおいしまこと)
- 弁護士(神奈川県弁護士会所属)
- 笑顔相続道®正会員
- 縁ディングノートプランナー™

「相続とおひとりさま安心の弁護士」大石誠 先生
平成元年生まれ 平成28年弁護士登録
横浜で、おひとりさま・お子様のいないご夫婦が、老後を笑顔で過ごすための終活・生前対策と、遺言・遺産分割をめぐる相続トラブルの解決を得意としています。
遺言、家族信託、後見、死後事務はもちろん、提携先の身元保証会社の紹介なども含めて、相続・終活についてワンストップで対応しています。
【筆者へのお問い合わせ先】
横浜平和法律事務所
- 所在地:横浜市中区日本大通17番地 JPR横浜日本大通ビル10階
- HP:https://ooishimatoko.threeways-labo.jp/
- 電話:045-663-2294