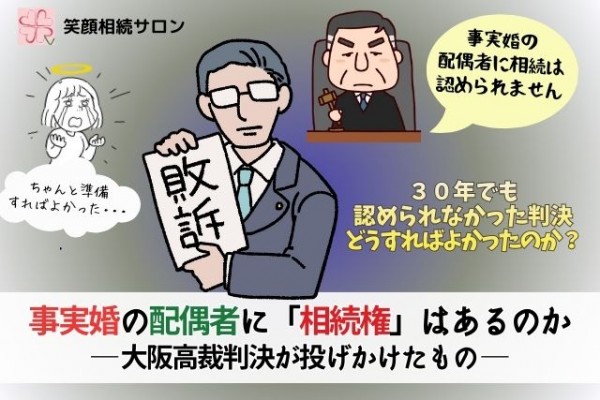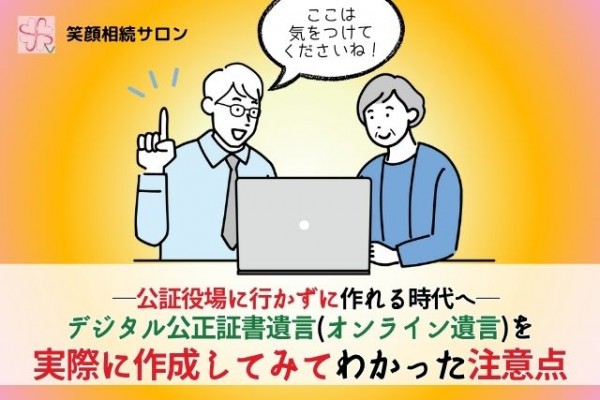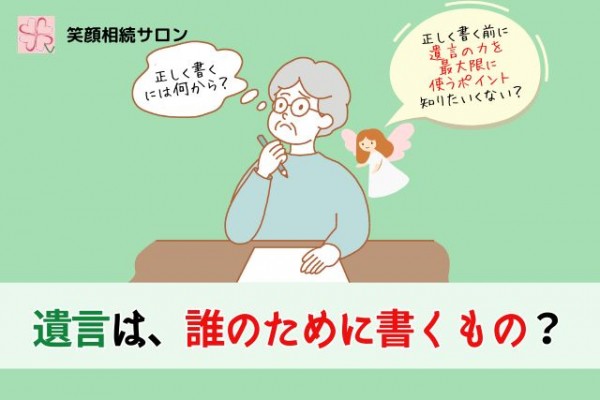民事信託の基礎知識とその秘めた可能性について
公開日:2025-03-31 00:00
目次
■ 従来の相続対策とどう違う?新しい資産承継の形
笑顔相続サロン 一橋香織 代表らの新刊『相続コンサルタントのための はじめての家族信託』を通じて、民事信託と生命保険信託について研鑽を深める機会がありました。

従来、伝統的な資産の承継方法というと、遺言か生前贈与の二択でしたが、近年、民事信託(家族信託)や生命保険信託といった手法も注目を浴びています。
また資産の承継という観点だけでなく、認知症による資産凍結対策としても、従来の任意後見・成年後見制度と比べて、自由度が高く、柔軟に資産管理が行える手法として注目されています。
相続の相談会に参加すると、次世代への資産の承継手段として、遺言書の作成で足りるというご相談が多いものの、例えば、「二次相続が生じた場合の移転先まで決めておきたい(後継ぎ遺贈)」など、ご希望に沿った資産の承継は、民事信託しか無いというご相談もあります。
今回は、民事信託の基本的な考え方とその可能性について解説していきます。
■ 民事信託の基礎知識
民事信託とは、図のとおり、財産の所有者(委託者)が、信頼できる第三者(受託者)に財産を託し、指定した目的にしたがって、信託の対象となっている財産(信託財産)を管理・運用・処分してもらう仕組みです。
この受託者の役割を家族が担うことから、商事信託と区別して、「家族信託」とも呼ばれています。
民事信託の契約が成立すると、信託財産の所有権それは自体は受託者に移転するため、委託者自身が認知症や病気で判断能力が低下した場合でも、受託者が継続して資産管理を行える点が特徴です。
例えば、認知症による資産凍結の回避や、収益不動産の円滑な承継などに広く活用されています。遺言や成年後見制度では実現が難しい柔軟な財産管理が可能であることから、特に最近、高齢社会を迎えた日本でその重要性が高まっています。

(法務局より引用;https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001354479.pdf)
■ 民事信託の典型的な活用事例
民事信託が実際にどのような場面で使われているのか、典型的な事例を挙げて解説します。
(1)認知症による資産凍結への備え
高齢の親が認知症になった場合に備えて、子を受託者として財産を管理してもらうというのが典型的な活用例です。
認知症などにより判断能力が低下すると、自身の銀行口座が凍結されたり、アパートなど収益物件の大規模修繕工事の契約ができなくなるという問題が生じます。また、これまで生活をしていた戸建てがあり、老人ホームに入居後も当面は売却しないものの、認知症の有無に左右されることなく、適宜のタイミングで空き家を売却したいというご相談にも対応することができます。
このように、民事信託を設定しておけば、受託者である子が引き続き財産管理を行うことが可能です。生活費や介護費用を確保し、親の生活を守るための仕組みとして高く評価されています。
(2)障害を持つ子のための福祉型の信託
障害を持つ子がいる親にとって、親亡き後の子の生活を守ることは切実な課題となります。
民事信託を活用すれば、親の死後も受託者が定められた目的のとおりに資産を管理し、障害を持つ子の生活費や医療費を継続的に支給することが可能となります。
親亡き後も子が安定した生活を送れる仕組みとして、福祉的な活用も増えています。
(3)不動産の共有回避と円滑な承継
複数の相続人がいる場合、不動産を共有すると、後に売却や活用方法で争いが生じやすくなります。
民事信託を活用することで、不動産の管理権限を一本化し、受託者が一元的に資産管理や売却の判断を行えるため、相続人間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
■ 民事信託の未知の可能性を探る試論
民事信託はまだ比較的新しい制度であり、これまで紹介した方法以外にも、事業承継への活用、上場株式の運用の継続など、様々な活用場面が登場します。
そこで、民事信託の未知の可能性を探る試論として、こういった場面で活用できないだろうかという私見を提示します。
(1)地域貢献の資産承継
まずは、「地域貢献型」と呼称して、地域活動や社会福祉事業に活用するというのはどうでしょうか。
遺贈寄付は、遺言によって相続財産を公益法人やNPO法人などの団体に寄付する方法ですが、これを民事信託で実現するという方法です。
例えば、「不動産を遺贈寄付したいが、他方で不動産を即座に売却処分されるのは本意ではなく、特定の用途で活用して欲しい」といったご相談を受けることがありますが、こういったニーズに合致するかもしれません。
(2)暗号資産の承継
また、暗号資産(仮想通貨)の承継に活用できないでしょうか。
信託法上、信託財産の種類や内容に制限はありません。
ネット証券やネット銀行が主流となり、紙媒体の通帳が廃止される中で、遺産の所在が分からないという問題が増えていますが、仮想通貨などの暗号資産の登場により、この問題がさらに顕在化する時代が到来すると考えています。
被相続人が心身共に健康なうちに、相続人に暗号資産の所在を把握させつつ、一方で、暗号資産を運用することによる利益は被相続人に還元することを実現できるのが、民事信託という手法になります。
ただし、預貯金の場合は、信託口口座を開設することで、受託者が信託財産と自己の財産とを分別して管理することができますが、暗号資産については、こういった実務上の諸問題への対応がまだ追いついていないのが現状です。
■ 民事信託は柔軟性と可能性がある
信託法の大家、故四宮和夫氏は、著作の中で、「信託は、その目的が不法や不能でないかぎり、どのような目的のためにも設定されることが可能である。したがって、信託の事例は無数にありうるわけで、それを制限するものがあるとすれば、それは、法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない」(有斐閣『信託法(増補版)』はしがき)と指摘されました。
民事信託は単なる資産保全の仕組みを超えて、個人の意思や家族の思いを次世代に確実に伝える新たな可能性を秘めています。今後もその柔軟性と可能性を活かした新しい活用法が次々と現れてくるでしょう。相続や終活の分野において、民事信託はまさにゲームチェンジャーとなる大きな可能性を秘めているのです。
【プロフィール】
大石誠(おおいしまこと)
- 弁護士(神奈川県弁護士会所属)
- 笑顔相続道®正会員
- 縁ディングノートプランナー™
- 「相続とおひとりさま安心の弁護士」
- 平成元年生まれ 平成28年弁護士登録
- 横浜で、おひとりさま・お子様のいないご夫婦が、老後を笑顔で過ごすための終活・生前対策と、遺言・遺産分割をめぐる相続トラブルの解決を得意としています。
- 遺言、家族信託、後見、死後事務はもちろん、提携先の身元保証会社の紹介なども含めて、相続・終活についてワンストップで対応しています。
- 横浜平和法律事務所
- 住所:横浜市中区日本大通17番地 JPR横浜日本大通ビル10階
- HP:https://www.ooishimakoto-lawyer.com
- 電話:045-663-2294